 政治・社会
政治・社会 【ドラッカーの思想】”時代遅れ” とされたキルケゴールの遅れようがない実存哲学(後編)
前回紹介したのは、ドラッカーがキルケゴールに学んだ人間の実存の定義だった。人間は社会的存在であると同時に霊的存在である。理性主義者は社会改良に力を傾けすぎて自滅し、猛烈な反理性主義の反動を引き起こしてホロコーストやスターリンの粛清を招いた。...
 政治・社会
政治・社会 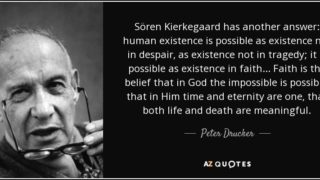 政治・社会
政治・社会  宗教
宗教  AI・自動化
AI・自動化  AI・自動化
AI・自動化  政治・社会
政治・社会 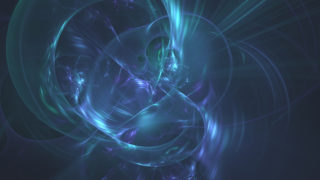 AI・自動化
AI・自動化  宗教
宗教 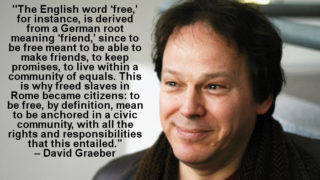 お金の話
お金の話  AI・自動化
AI・自動化 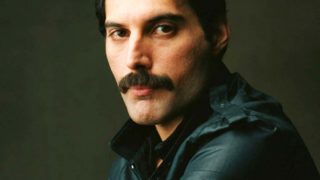 ♪音楽
♪音楽 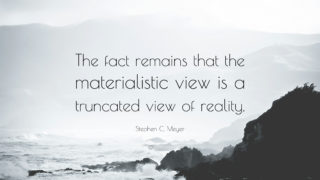 政治・社会
政治・社会  ♪音楽
♪音楽  歴史
歴史  宗教
宗教