 Web紀行
Web紀行 【ロシアとウクライナ】独立自治をめぐる仁義なき “宗教” 代理戦争
ウクライナ独立の動きは政治マターから宗教マターへ展開し始めた。正教会という精神的紐帯の破壊を狙ったCIAによるプーチンへの揺さぶりだろう。今回は日本人にはなじみの薄いキリスト教正教会(ギリシャ正教)に絡んだお話である。
 Web紀行
Web紀行  政治・社会
政治・社会  Web紀行
Web紀行 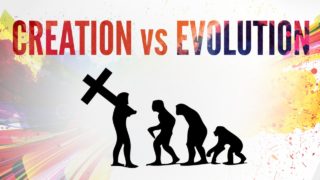 宗教
宗教  政治・社会
政治・社会 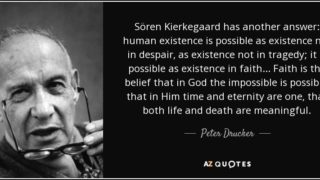 政治・社会
政治・社会  AI・自動化
AI・自動化  政治・社会
政治・社会  宗教
宗教 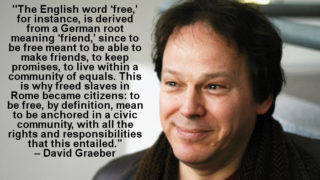 お金の話
お金の話  AI・自動化
AI・自動化 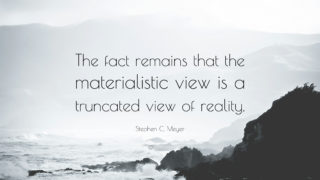 政治・社会
政治・社会  政治・社会
政治・社会  宗教
宗教  お金の話
お金の話