【時事ネタ】セクハラ・パワハラ問題と父権社会のリバランス運動
2018.5.29 記事後半を全面改稿
今回は「深淵について」シリーズからのスピンオフ投稿になる。
このシリーズ記事を書いたきっかけはゴールデングローブ賞の授賞式の写真だった。例年なら露出度を競うアメリカ女優たちが揃いも揃って黒ずくめの衣装で彼の舞台に登場。ただならぬ雰囲気を感じた。
黒ずくめは欧米で伝統的なプロテストの意思表示方法である。彼女たちは本気で男社会の因習と戦おうとしている。
しかも・・・黒・・・女性・・・
黒い女神!
カーリー!

これは深いところから来る動きに違いない。
・・・と書いたところへ、日本でもちょうど伊調馨と栄コーチのパワハラ・スキャンダルで騒がしくなっている。本人は告発状への関与は否定しているので、例によって例のごとく人権派弁護士の関与が疑われるところだが、本人が事実関係まで否定しているわけではない。火のないところに煙は立たない。
やはり、奥深いところで女性たちは共鳴し合っているようだ。
ワインスタイン効果
#MeToo運動や#TimesUp運動の発端となった事件は、大物映画プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインに対する女優たちの告発であったことから、昨秋来の現象をワインスタイン効果(Weinstein Effect)と呼ぶ。wikipediaから一部を訳出してみよう。
The “Weinstein effect” is a global trend in which people come forward to accuse famous or powerful men of sexual misconduct. The term came into use to describe a worldwide wave of these allegations that began in the United States in October 2017, when media outlets reported on numerous sexual abuse allegations against film producer Harvey Weinstein.
Described as a “tipping point” or “watershed moment”, the Weinstein allegations precipitated a “national reckoning” against sexual harassment. USA Today wrote that 2017 was the year in which “sexual harassment became a fireable offense”.
ワインスタイン効果とは女性が自ら名乗り出て、男性有名人または有力者から受けた違法性行為を糾弾する世界的なトレンドのこと。2017年10月にアメリカで始まり世界的に広がった申し立ての連鎖を表す用語となっている。きっかけは映画プロデューサーのハーヴェイ・ワインスタイン氏による数十件の性的いやがらせに対する申し立てがあったと報じたニューヨークタイムス紙の記事である。
ワインスタイン氏への集中的な申し立ては、セクハラに対する「国家的裁き」を促進した転換点もしくは分水嶺と目されている。USAトゥデイ紙の表現を借りれば、2017年は「セクハラでクビにできる」年となった。
直ちにクビ切りにつながるような重大な悪事(違反行為・犯罪)のこと。
ワインスタインの会社は事件から4か月で破産に追い込まれた。弱り目に祟り目だったらしいが、それにしてもこのスピード感は尋常ではない。HuffingtonPost紙の関連記事から一部を引用する。
報道によると、近年はヒット作に恵まれず、経営が悪化していたところにセクハラ問題が表面化。制作会社から取引を打ち切られるなど、窮地に追い込まれた。投資グループへの売却を模索していたが、交渉がまとまらなかったという。
とうとう始まった「女性」の反撃
「深淵」シリーズの最後にトコシエは以下のように書いた。
彼女(※カーリー)は我々人間のこころの持ちようを反映する。神とはそういうものなのだと、古代人の叡智は見抜いていた。
現代社会のありとあらゆる問題は、ロゴス中心に定義し直された神(実体化、男性性による虚構化)による、本当の神への違背に基づいているともいえる。
「本当の神」というのを実体的に考えてほしくない。なぜなら神とはカーリー神の三相一体性が示すように、不変のスタティックな存在ではなく、ダイナミックに「人間のこころの持ちようを反映する」ものからだ。神にかたちはなく、遺伝学でいうミームのように世代間で転写され、時の移ろいとともに相が入れ替わっていくイメージである。
トコシエが一神教問題にこだわってきたのも、神を固定化する一神教の世界観、世界を善悪で裁こうとする思い上がり、その背景にあるロゴス中心の、いわゆる男社会の築いてきた2000年の歴史への違和感があるためだ。ありがたいことに、そのゴリゴリの男社会の賞味期限が迫っているような気がするのだ。性的頽廃をセクハラで晴らし、権力欲求をパワハラで満たすような男どもはどんどん制裁を受ければいい。
反撃の狼煙をあげてくれたのは女性たちである。彼女らはやはり「生む」存在である。人類社会が危機的な様相を呈すれば、女性の奥深くにしまわれているセンサーが反応し、共鳴を起こす。そしてカーリーの破壊神としての相が顕在化してきている。だから一連のワインスタイン効果は一過性の現象ではないと見ている。
「男オンナ」の急増が懸念材料
ただ、ひとつ懸念がある。女性のなかに「男オンナ」が増えていることだ。「男オンナ」が女性の足を引っ張りかねない。
「男オンナ」たちが何となく奉じている宗教はネオリベラリズムと呼ばれている。しかし彼女らに考えてみてほしいのは、そのネオリベ思想こそ男社会のパワハラ文化、セクハラ文化を延命させている温床だということなのである。
父権社会への道
どういうことか?それを説明するために、現在に至る歴史を駆け足で振り返ってみる。
事の起こりはユダヤ・キリスト教による宗教革命である。

女性が強かったのは農耕社会だけではない。たとえば、黒海の北岸にサマルタイ(Sarmatian)という部族(スキタイ人)が連合国家を営んでおり、たびたびギリシャ人と衝突していた。サマルタイにはギリシャ人がアマゾン(アマゾネスは複数形)と呼んで蔑んだ屈強な女性戦闘軍団があったという。ギリシャはすでにマッチョな男社会で、政治や戦闘や学問や哲学をやる人間は有閑階級の男に決まっていた。
ギリシャからアレクサンダー大王が出て、ペルシャ帝国を滅ぼすと古代の先進地帯で一気に東西の文化混淆が進む。この文化習合の中から、農耕に関係しない遊牧民ヘブライ人が、男性神をベースに唯一無二の普遍神を創造する。
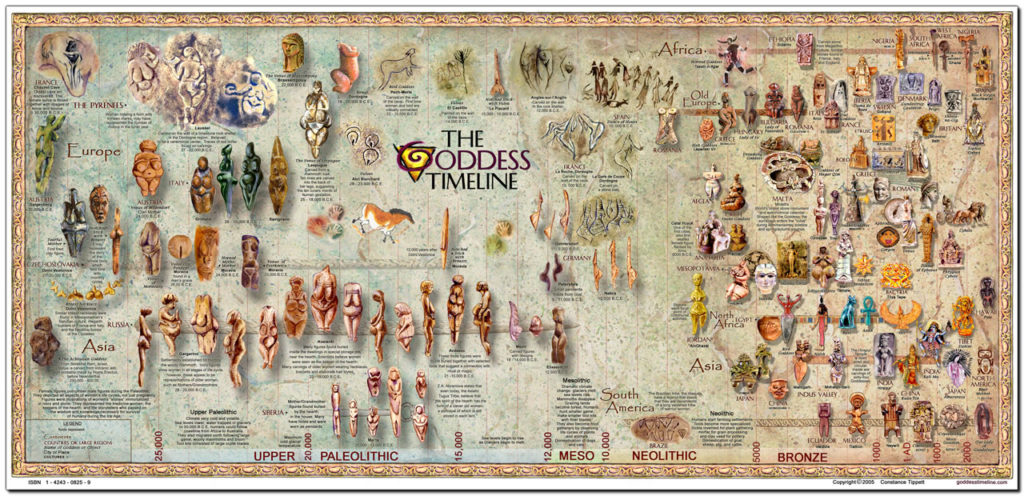
ユダヤ・キリスト教による男性原理の確率
一神教登場の背景には帝国化の現実があった。農耕民を支配した王権は国家を築くが、やがて国家と国家の争いの中で帝国が生まれてきた。そうなると国家レベルの神では通用しなくなる。ペルシャ帝国は宗教に寛容であったがゆえに滅びたともいえるのだ。ましてや女神は邪魔になる。民俗や風習の違う国でも拝めるような、無色透明の神が必要になってきたのである。
一神教の特徴は、母権社会以来の伝統だった偶像崇拝の禁止と、禁欲の奨励だ。偶像は具体性であり、大地のシンボルだ。肉欲に代表される欲望追求に女性は欠かせない。たとえば、現世利益の否定は、以下の聖書の物言いに象徴されている。
Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—comes not from the Father but from the world.(First Letter of St. John 2:15-16)
世も世にあるものも、愛してはいけません。世を愛する人がいれば、御父への愛はその人の内にありません。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは、御父から出ないで、世から出るからです。(ヨハネ第一の手紙第2章15-16節)
「世にあるもの」とは女性原理のメタファーである。創世記ではイヴ(最初の女性)はアダム(最初の男性)のあばら骨からつくられたという荒唐無稽まで信じろという。
ここまで徹底して女性を貶めたいのはそれだけ女性を恐れていた証拠かもしれないが、とにかかくヘブライ人は「これからは男が仕切りますよ」と宣言して、なぜかローマ帝国の支持まで取り付けてしまうのだ。
世界は不思議なもので、こうしたトンデモ少数派の思想がその後の超メジャーに育ってしまうのだ。ローマを制すれば後は追って知るべし、”蛮族” ゲルマン人を数百年の時間を掛けながら徐々に改宗させ、男性(父権)的キリスト教の天下を作り上げる。女性は男社会の中でずっとハンデ戦を戦うことになった。少なくても社会的には。
「男オンナ」は貨幣グローバリズムの延命策
神を司る教会が世俗権力と癒着して信用を失い始めると、経済力をつけた商人や金融業者へ権力が集まり始める。そして宗教改革でカトリック教会の力をそぎ、フランス革命で王の力を奪う。これは平民に私有財産を与え、私有財産をベースに自由を与える動きでもあって、基本的には大きな支持を得た動きだったから、現代まで持続してきたのだ。
近代社会の特徴は、人間の自由の担保を神ではなく貨幣に求めた点にある。無色透明で抽象的な貨幣というメディアは、数量化できて便利だし、子孫に相続可能だし、個人の生涯にとっても家族の存続にとっても、また国家観のパワーゲームの価値基準として、たいへんよく出来た神の代替手段だったのである。
18世紀から20世紀にかけては、平民がまだ自由に慣れておらず、利殖・蓄財に燃えている時代だったから、多少の不都合は目をつむってとにかく自由の追求が第一の行動原理となり、社会発展の原動力となった。途中で行き過ぎた自由化と拝金主義に嫌気がさし、私有財産を否定する天邪鬼な社会主義・共産主義という新興宗教が誕生して一世を風靡したが、今日ではからっきし人気がない。
ひとたび先進国の平民に所得と自由が行き渡った21世紀になると、貨幣の暴れぶりが目立ち始め、自由を手にした平民間で格差感覚が拡大して、これまでの自由至上・私益追求のグローバリズムに疑念が生じ始めた。そして、ここが問題だが、男社会の貨幣グローバリズムは最後のフロンティアとして “女性市場” に手を付け始めたのだ。
これまでの禁制を解き、”女性活躍社会” を言い始めたのは、女性のためではない。男社会の貨幣グローバリズムを延命させるためである。男たちがそんなに簡単に既得権益を譲渡するわけないではないか。
つまり男になりたがる「男オンナ」が増えれば増えるだけ、そろそろ賞味期限が来ているはずの男社会が「男オンナ」の加勢を得て延命してしまうのだ。反撃に出始めた女性にはくれぐれも「男オンナ」にならないようお願いしたい。




-100x100.jpg)



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません