当サイトの人気記事「英語は思ったよりラテンなゲルマン系言語」でも似たようなことを書きましたが、英語は「ローマの教養を身につけた海賊たち」の言語だといえます。根っこのゲルマン魂はさておき、英語はラテン語の洗礼を受けることで文化的に洗練されていったのです。その功績はキリスト教の聖職者とフランスから進出した支配層にあります。
三度にわたるラテン語系語彙の流入
逆に、英語ネイティブの本音の本音の部分はいまもゲルマン系語彙が支えています。面白いことに、イギリスにはラテン語の影響のない古英語で書かれた叙事詩「ベオウルフ」(Beowulf)が現存していて、これは日本人にとっての万葉集に相当するような言語遺産です。以下の動画でどんな響きを確認できますが、およそ現代英語とは似ても似つきません。
異民族の混淆とキリスト教伝来
大陸の西に浮かぶ島国のイギリスには太古から多くの異民族が進出してきました。最初はケルト人。次にローマ人。そして、後にメジャー勢力となるゲルマン系諸民族(アングル人、サクソン人、ジュート人、デーン人。前三者がいわゆるアングロ・サクソン人の母胎)。そして11世紀後半フランスから渡ってきてイングランドを支配したフレンチ・ノルマン人(先祖は北欧の海賊なので、アングロ・サクソン人と似た出自)です。
英語の歴史を考える上で決定的な影響をもたらしたのはキリスト教です。ブリテン島が古代ローマの支配下に置かれていた時代、キリスト教は一時的に広まったのですが、ローマ軍が引き上げ、5世紀後半に異教徒のアングロ・サクソン人が進出してくると一気に廃れてしまいます。彼らはベオウルフに記録されたような純粋ゲルマン語系のことばを話し、その世界観もキリスト教のそれとはまったく違っていたからです。
ところが、キリスト教はアングロサクソンの進出しなかったアイルランドに根を張っていました(ケルト系キリスト教)。そこから修道士がスコットランドやイングランド北部に修道院を構え、熱心に布教を行ったのです。
これとは別に、6世紀終わりにはローマ教皇グレゴリウス1世が、イングランド南部のケントにアウグスティヌスを派遣し、正式に布教を開始しました。
つまり、イギリスのキリスト教化には2つの潮流が存在したのです。両者の盛衰を決めたのは、アングロ・サクソン人の後に進出してきたデーン人でした。以下、wikipediaから引用します。
異教のアングロサクソン・イングランドを再び教化したのは、ローマ教皇グレゴリウス1世に派遣され、597年ケントに上陸したカンタベリーのアウグスティヌスが率いる宣教団だけではない。アイルランドからヘブリディーズ諸島に渡った聖コルンバが創建したアイオナ修道院はスコットランドを教化したし、アイオナからノーサンブリアに移植されたケルト教会であるリンデスファーン修道院は北部イングランドを改宗させている。またこれらの修道院からケルト系修道院制度が海を渡って現在のオランダやドイツにまで伝えられた。
中世ケルト教会の中心となったアイオナ修道院やリンデスファーン修道院が9世紀にヴァイキングの度重なる襲撃によって荒廃すると、いつしかベネディクト会修道院にとって代わられ、ケルト系キリスト教は歴史から姿を消した。

ブリテン・キリスト教史の転換点となったウィットビー宗教会議(Whitby Synod)。ケルト系キリスト教会は衰退し、ローマ・カトリック教会が主流化した(写真はウィットビー修道院の廃墟)。

北部中心だったブリテン島の発展は、この時代から次第に南下を始め、宗教的にはカンタベリーが、政治経済的にはロンドンが中心の歴史に収斂していきます。
聖書の英語化とルネサンス
キリスト教の聖典はラテン語訳聖書であり、一部の聖職者しか読むことができませんでした。イングランド民衆に教えを広めるには聖書を英訳する必要があります。このときラテン語語彙の英語化が発生し、その後の英語に深く影響していきます。
11世紀終わりに進出してきたノルマン人がアングロ・サクソン人を征服したとき、今度は統治(行政や法律)のための概念が、ラテン語を祖とするノルマン・フレンチ経由で大量に英語に流れ込みます。
その後、ルネサンスの時代には大陸文化の摂取が盛んになり、今度は文化領域(思想、芸術、文芸)のラテン系語彙も借用され始めるのです。
このように何度も押し寄せるラテン語伝播の波に晒されながら、現代に至る英語の骨格が出来上がっていったのです。

英語形成史(出典: https://triangulations.wordpress.com)
ラテン語伝播の大波は前後3回に渡って来ていますので、それぞれの内実を少し詳しく見ていきましょう。
接触1:英語発生以前=ローマ帝国の支配(Roman Occupation)
アングロ・サクソン人の進出以前、ブリテン島はローマ帝国が支配しており、キリスト教も伝えられていました。当然ラテン語は入ってきたはずですが、当時のネイティブ住民はブリトン人(ケルト系言語の話者で、スコットランド人、ウェールズ人、アイルランド人、フランス・ブルターニュ地方住民などの先祖)だったので、アングロ・サクソン人のことばである古英語への影響はほとんど認められません。
しいて言えば、アングロ・サクソン人とブリトン人との接触から、strǣt(streetの元、語源はラテン語のstrǣta)などわずかなラテン系語彙が借用されました。
接触2:古英語(Old English)期=アングロ・サクソンとデーン人の進出(Germanic Settlements、Viking Invasions)
英語の大元(古英語、Old English)を作ったのは、デンマークや北部ドイツからグレートブリテン島に侵略したアングロ・サクソン(アングル人、サクソン人、ジュート人)です。彼らヴァイキングは海を伝って各地を転々とするせいか、土着文化には無関心、文化的洗練など二の次です。ことばや宗教に関しても同じで、他人のものを平気で採り入れます。
ブリテン進出以前の借用語
アングロ・サクソンはグレートブリテン島に進出する以前から、北方進出を進めるローマ軍とやり合い、ラテン語と接触していました。当時はゲルマン人の生活水準の向上が急務で、ローマの学問、宗教、芸術など文化的語彙よりも、日常生活や貿易、商業に関わる語彙を多く受け入れました。そのため、主に名詞を借用語として採り入れ、短くシンプルな語が多いのが特徴です。以下に例を示しましょう。
- camp(語源はラテン語のcampus)
- mynet(moneyの元、語源はラテン語のmoneta
- coper(copperの元、語源はラテン語のcuprum)
- belt(語源はラテン語のbalteus)
- sīric(silkの元、語源はラテン語のsēricum)
- socc(shoe、sockの元、語源はラテン語のsoccus)
- candel(candleの元、語源はラテン語のcandēla)
- butere(butterの元、語源はラテン語のbutyrium)
- wīn(wineの元、語源はラテン語のvīnum)
- ceaster(cityの元、語源はラテン語のcastra)
- cycene(kitchenの元、語源はラテン語のcoquīna)
- līne(語源はラテン語のlīnea)
- weal(wallの元、語源はラテン語のvallum)
- plante(plantの元、語源はラテン語のplanta)
ブリテン進出後の借用語:キリスト教布教前
キリスト教が伝道される前の時代は、引き続き生活水準の向上に主な関心が向けられていました。
- copp(cupの元、語源はラテン語のcuppa)
- catt(e)(catの元、語源はラテン語のcattus)
- cocc(cockの元、語源はラテン語のcoccus)
- munuc(monkの元、語源はラテン語のmonachus)
- mynster(minsterの元、語源はラテン語のmonasterium)
- nunne(nunの元、語源はラテン語のnonna)
ブリテン進出後の借用語:キリスト教布教後(~ノルマン・コンクエスト以前)
6世紀終わりに聖アウグスティヌスがイングランド南部のケントに上陸してキリスト教の布教を始めると、南部のアングロ・サクソン人を中心に彼らは次第に在来信仰を捨て改宗して教に改宗していきます。
アイルランドに発しスコットランド、ノーザンブリアの改宗を進めていた修道士(monk)中心のケルト系カトリックが、司教(bishop)中心の布教を行うローマ・カトリックの勢力と拮抗し、お互いの妥協できない違い(復活祭の算定方法など)を解消すべく宗教会議を開いた地が北海沿岸の港町ウィットビーでした。ウィットビー宗教会議(Whitby Synod)はイギリスのキリスト教にとって天下分け目の「決戦」となったのです。
これ以降、イギリスの政治文化の中心はウィットビーのあるノーザンブリアからウェセックスやケント(ローマ・カトリックの総本山カンタベリー)の南部に移り、キリスト教関連はもちろん、ローマの文化・学問に関する語彙が多く、アングロ・サクソンの標準語となったウェセックス方言に借用されていきます。
- (a)postol(apostleの元、語源はラテン語のapostolus)
- cleric(clerkの元、語源はラテン語のclēricus)
- crēda(creedの元、語源はラテン語のcrēdō)
- diacon(deaconの元、語源はラテン語のdiāconus)
- discipul(discipleの元、語源はラテン語のdiscipulus)
- mæsse (or messe)(massの元、語源はラテン語のmissa)
- martir(martyrの元、語源はラテン語のmartur)
- offrian(動詞offerの元、語源はラテン語のofferre)
- pāpa(popeの元、語源はラテン語のpāpa)
- paradīs(paradiseの元、語源はラテン語のparadīsus)
- prīor(priorの元、語源はラテン語のprior)
- tempel(templeの元、語源はラテン語のtemplum)
- spendan(動詞spendの元、語源はラテン語のexpendere)
- scōl(schoolの元、語源はラテン語のschola)
接触3:中英語(Middle English)期=ノルマン・コンクエストとプランタジネット朝
ラテン語系語彙が英語に不可逆的とも言える決定的な影響を及ぼしたのは、11世紀終わり、フランスのノルマンディ地方にいた、やはりヴァイキングの末裔であるノルマン人がイングランドを征服して以降です。それまでの宗教権威の上に、今度は政治経済の力が加わったからです。
ノルマン人(ノルマンディー公)はノルマンディに移住する際、祖語のゲルマン語からフランス語に切り替え、ノルマン・コンクエストの時代にはゲルマン訛りのフランス語「ノルマン・フレンチ」(ロマンス語の一派オイル語に属す)を話していました。
しかしノルマン王朝の支配は長くは続かず、12世紀中盤、フランス本土に広大な領土を持つアンジュー伯アンリ(ヘンリー2世)がイングランド王となり、プランタジネット王朝を開きます。アンジュ―家の話すフランス語はパリで話される「セントラル・フレンチ」でした。
ノルマン・フレンチvsセントラル・フレンチ
このため英語に入ったラテン語系語彙の多くはノルマン・フレンチかセントラル・フレンチのどちらかです。両者の違いを糸口にすれば、ボキャブラリーの拡充に役立ちます(英語に意味が似ていて違う単語=異音同義語が多く存在するのはこの支配階級の変遷によるものです)。
同じラテン語を語源としながら、ノルマン・フレンチとセントラル・フレンチの音韻(発音)のクセが出て、違う単語として英語に「登録」されたケースは珍しくありません。これを二重語(doublet)と呼びます。
二重語
13世紀までにノルマンおよびセントラルから約10,000のフランス語語彙が古英語に取り込まれたと言います。そのうち3/4ほどは現役だそうで、同じような意味の古英語とフランス語が共存しているケースが珍しくありません。
例:
- doom(古英語)とjudgment(フランス語)
- hearty(古英語)とcordial(フランス語)
- house(古英語)とmansion(フランス語)
フランス語から中英語に採り入れられた単語
以下、いちいち語源を示すのはやめますが、フランス語から中英語に入った代表的な単語を分野別にピックアップしてみました。
宗教関連
Genesis、Exodus、requiem、gloria、limbo(辺獄、洗礼の恵みを受けぬ者が死後に行き着く場所の意)、magnificat、collect、bull、mediator、redemptor、salvator、psalm、apocalypse、magi(magicの語源、ペルシャの僧)など。
法律関連
client、arbitrator、conviction、equivalent、extravagant、executor、implement、legitimate、memorandum、persecutor、proviso(法律の但し書き)など。
学術関連
allegory、et cetera、cause、contradictory、desk、explicit、formal、index、item、library、major、minor、neuter、scribe、digit、orbit、dislocate、recipe、dissolve、ether、mercury、concatenate、concrete、elixir、essence、fermentation、fixation、obscuration、ascension、comet、dial、eccectric、equal、equator、intercept、juniper、pine、locust、onyxなど。
近代英語(Modern English)期の借用の嵐
以上の3度にわたる接触期を経て、英語が最もラテン系語彙の大量借用を行い始めたのは、16世紀後半から17世紀前半にかけてのルネサンス全盛時代です。ノルマン・コンクエストの影響で本来の造語能力を奪われた英語は、新概念や新知識をラテン語(学術系ではこれにギリシャ語)の借用で補うしかなかったのです。
長大なリストを掲げるのも気が引けるので、年代順に代表的な借用語だけリストアップしておきます。
16世紀前半
integer、genius、junior、vertigo、alias、area、exit、peninsula、regalia、abdomen、animal、appendix、circus、interim、axisなど。
16世紀後半
vacuum、medium、species、caveat、multiplex、innuendo、codex、omen、militia、cornucopia、radius、stratum、virusなど。
17世紀前半
premium、equilibrium、specimen、series、census、plus、tenet、par、arena、apparatus、veto、flat、curriculum、query、formula、impetus、plebsなど。
17世紀後半
copula、album、complex、vortex、pendulum、minimum、dictum、calculus、stimulus、lens、status、antenna、momentumなど。
18世紀前半
nucleus, cirrus, caret, inertia, locus, propaganda, alibi, auditorium, ultimatum, maximum, etc.
18世紀後半
insomnia、bonus、extra、prospectus、via、deficit、tandem、habitatなど。
19世紀前半
opus、duplex、ego、incunabula、omnibus、sanatoriumなど。
19世紀後半
aquarium、consensus、moratorium、referendumなど。
言語の保守性:口語の7割以上はゲルマン語彙
言語の保守性というのか、人間の血やDNAは戦争や侵略を経ても強固にオリジナルを守り継ぐようです。2万語以上とも言われる大量のラテン系語彙の流入・借用にもかかわらず、現代の英語ネイティブが日常的に話す7割以上の単語(口語、colloquial English)は古英語にルーツを持つと言います。
ちなみに、colloquialということばそのものも「会話」を意味数るラテン語から来ています。

1751, “pertaining to conversation,” from colloquy “a conversation” + -al (1). From 1752 as “peculiar or appropriate to the language of common speech or familiar conversation,” especially as distinguished from elegant or formal speech.
日本語も似た事情:仏教語の影響
現代に、異文化の影響が一切ない純粋言語などほぼ存在しません。みんなハイブリッドなのです。日本語も同じで、日本語には当時の先進国(政治大国)だったシナから大量の借用語が持ち込まれました。ところが、現代日本人の日常語の多くは依然として「やまとことば」です。例えば、
それって違うと思うよ。
とは言いますが、
それって違うと思考するよ。
とは言いません。「それ」「ちがう」「おもう」、すべてやまとことばです。
日本語にとってラテン語に当たるのは中国語ですが、なかでも仏教語の影響が強いように思います。やまとことば以外でよく使われる語彙を見ると、中国起源のことばより、中国訳仏教語の数々が多用されているからです。
例えば、以下の文の青字にした単語はすべて仏教から来ています。
あの子は愛嬌があるね。それにどことなく上品だ。
念願の出世がかなうのか、ここが正念場。
旦那には内緒よってあれだけ言ったのに、ひどい。我慢できなかったの?
古代インドに生まれた仏教。サンスクリット語の原典が中国訳され(意味ではなく音を中国に移した音訳と、音ではなく意味を移した意訳の二通りがあります)、この音訳と意訳の双方が日本語へ移入されました。その後、仏教の概念は日本人の精神生活に大きな影響を与えると同時に、日本人の方でも元の仏教概念を独自に解釈し直し「日本化」していきました。
そうこうするうちに、仏教はそれとは意識されないレベルまで日本人の考え方や感じ方、あるいは日常成果の立ち居振る舞いに深く浸透していったのです。もちろん最基層には、在来の神道的な、あるいは神道以前の縄文的な要素があるのですが・・・。
これは英語世界でも、キリスト教に由来する概念や習慣が深く生活や思考様式に浸透しているのと似ています。でも、ネイティブの無意識のなかにはキリスト教的世界観ではとらえきれないものがあり、そういうものがつまっているのがゲルマン系の基礎語彙なのだと思います。だから、しっかり命脈を保ってきたのでしょう。





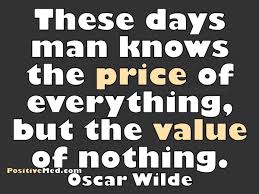

コメント