【令和の令】令はbeautifulじゃなくauspicious?鳥占いとエトルリアの影
元号をいまも続ける国は多くありません。日本の場合、元号は「時代」を作ります。「昭和だねぇ」と言えば、それがわかる人たちの間に連帯感やノスタルジーが生まれます。そのうち「ああ、平成だよね」という感覚が生まれるでしょう。いまは若い平成生まれの人たちも、令和生まれに「う、平成くさ」と「括られる」日が来ます。
元号と「いのち」の感覚
元号は太古からの日本人の感覚を反映しているように思います。私たちの先祖は、この世界(天地)は終わりも始めもないと見て、その状態を「いのち」と呼んでいました。いまは「いのち」というと、生き物のエネルギーの継続か、生まれて死ぬまでの「生涯」を意味します。でも太古の人々の感覚では、万物、宇宙そのものが「いのち」で、個体の生は「いのち」の句読点のようなものなのでした。
唯一神が天地を創造したとする一神教とは対照的な世界観ですが、一神教は悠久の人類史から見れば「新興宗教」です。日本人は知らず知らずのうちに、元号のしきたりを守り、有史以前の世界観を「いまに生かしている」のではないでしょうか?
元号は「日本」に打たれた句読点です。ある人々の生きた時間に名前を与えます。過去をひもとくと、天変地異や政治的激動、天皇の譲位など様々な理由で改元されてきたようですが、共通するのは「けじめ」の感覚でしょうか。今般は平成天皇が自ら「けじめ」を表明されたのをきっかけに令和への改元が実現しました。
令和の令は命令や法令の令?それとも?
しかし一神教の世界観が主流化した現代では、元号の解釈もいま風です。欧米の主流派メディアは、この国が少しでも「おかしな」素振りを示すと、すかさず牽制してきます。その典型例が、次の一節です。これはJapan Timesの記事の抜粋ですが、令和の令の字を、命令や法令の令(いいつけ、きまり、おきて)と一義的に解釈し、安倍政権の「権威主義的」傾向と結びつけています。
The foreign ministry’s attempt to dissociate Reiwa from the authoritative nuance of command or law chiefly associated with rei, which is used in terms such as meirei (command) or hōrei (law), may have been clear enough from its issuance of the translation “beautiful harmony.”
日本政府のぱっとしない対応
政府は慌てて “beautiful harmony” といかにも速成の、役人的「直訳」を提示し、これをもってReiwaの公式なEnglish translationとしたいようです。『美しい国へ』の著作もある安倍首相には「美しさ」へのこだわりのようなものがあり、今回も「この令和には人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味が込められております」と言っています。この「美しく心を寄せ合う」という、日本人にもパッとイメージの湧きにくい表現を、英文記者は苦労して次のように訳しています。
“culture born and nurtured as people’s hearts are beautifully drawn together.”
draw togetherを使い、人々の心が美しく「ひとつにまとまる」「通い合う」「むつみ合う」といったニュアンスに落とし込んでいるわけです。ただ、令和の出典は九州大宰府で催された宴とのことですから、地方分権を進め、地方と地方が「美しく心を寄せ合う」ことを願う、とも解釈可能ではないかと思います。
それにつけても残念なのは、こういう場合の政府のあざなりな対応です。”beautiful harmony” はいかにも役人的な「建前と綺麗事」の凡庸を絵に描いたような直訳です。あれだけグローバル、グローバルと言っているのに、なんというアピール下手でしょうか。
令月の令は吉兆
むしろウォールストリート・ジャーナルの英訳 “auspicious harmony” の方を採用した方が面白かったと思います。万葉集出典の「令月」の令に即した訳になっているからです。古代人が陰暦二月を「令月」ーめでたき、良き月ーと呼んだのは、わずかに芽吹く木や早咲きの花々に、auspiciousな(幸先のいい、吉兆の)感じを感じたからでしょう。
令和という年号には、日本人の「和」の特性を十全に発揮できる未来へ向けて、これからの数十年(?)を幸先のよい時代にしたい、という願いが込められているように思われます。安倍内閣は「日本を取り戻す」と言ってきたのですから首尾一貫しているではありませんか。70年あまり堆積してきた「戦後レジューム」を安倍総理一代で払拭できるはずもなく、彼に「吉兆」以上を期待するのはかわいそうです。
But that rendition of Reiwa fails to reflect the original context in which the kanji rei was used in “Manyoshu” — the nation’s oldest existing anthology of poetry, from which the new gengō was drawn.
Reiwa was inspired by a portion of a passage written by prominent poet Otomo no Tabito, who used rei to render reigetsu, an “auspicious month,” as he detailed the soft manner of an early spring breeze.
令和の典拠となった大伴旅人の「令月」は英語では “auspicious month” と訳されています。ここでの令は「よい兆し」「吉兆」を意味しているからです。梅が桜の前兆であるように「先行きが明るい」「よい兆し」というイメージは、やがて令嬢、令息、令名というように「立派な」を意味する敬称へ転化していきました。
令和を桜咲く未来の日本につながる「幸先のよい」時代にしたいものです。
鳥占い(ornithomancy、またはaugury)
auspiciousということばは、例によって英語に大量に入ったラテン系語彙のひとつ。語源はauspex(”bird wather”、同義語augur)。auspexやaugurは鳥占い師(卜占官)のこと。古代ローマでは、卜占官の鳥占いで、吉兆の支持が得られなければ大事な政治行動は行えなかったそうです。
古代ローマの公的占い役。複雑な方式に従い天空や鳥の飛翔,鳴声,戦場では餌をついばむ鶏などを観察して神意を探る。不時の予兆も解く。卜占権はインペリウム(※最高公職者権限)に属し,最高公職者は就任にも民会召集・外征などの国事にも,そのつど占卜官に凶兆の有無を探らせ,神意にかなう行動を期した。
エトルリアの影響
鳥占いはローマの風習ではなく、隣接するエトルリア(Etruria、現在のトスカーナ州)の独自文化を採り入れたようです。
ちなみにエトルリア学者は、auguryを卜占総体を指す用語として使い、卜占を構成する部門として鳥占い(auspicy: bird-divination)、雷占い(brontoscopy: divination of lightning and thunder、thunderは雷の音、lightningは雷の閃光)、肝臓占い(haruspicy: liver-divination、動物供犠の肝臓を使う)があったと考えているようです。
ローマと言えばギリシャの影響ばかりが云々されますが、実はエトルリアこそローマの躍進の基礎を固めた偉大な文明です。このことについては、次の記事がよくまとまっています。
エトルリア人の精神の一端は、次の短い言及にあらわれています。
彼ら(エトルリア人)はまた、鳥占いや肝臓占い(動物の肝臓を取り出して吉凶を占う)などを行っていたが、これはアジアに源流があると考えられている。
鳥占いに由来する英語
鳥占いに関連して、英語の勉強にもなる部分を、wiki英語版のOrnithomancy(鳥占い)記事から紹介しましょう。
https://en.wikipedia.org/wiki/Ornithomancy
Omens from observation of the flight of birds were considered with the utmost seriousness by Romans. The practice of ornithomancy by priests called augurs was a branch of Roman national religion from before the founding of the city, which had its own priestly college to supervise its practice.
The word “inauguration” is derived from the Latin noun inauguratio derived from the verb inaugurare which was to “take omens from birds in flight.” Since Roman augurs predominantly looked at birds for omens, they were also called auspex (“bird watcher”, plural auspices), however they also interpreted thunder, lightning, the behavior of certain animals, and strange events. The phrase “under the auspices” is derived from this need for a favourable reading of the omens by the augurs.
ローマ人は鳥の飛行を観察して得られた吉凶を、この上ない真剣さで受け止めた。鳥占いを生業とする聖職者(卜占官)をアウグルという。アウグルはローマの国家宗教の一部門を成し、専門のカレッジを有していた。
英単語 “inauguration”(現代では、ほぼ米大統領の就任または就任式を意味する)の語源はラテン語の名詞inauguratio。動詞形のinaugurareは「鳥の飛行から前兆を読む」の意。ローマのアウグルは主に鳥を見て前兆を読み取るので auspex(鳥観察者の意、複数形はauspices)とも呼ばれたが、他に、雷や稲妻、特定の動物の挙動、未知の事象なども解釈した。”under the auspices”(支持・支援のもとに) というイディオムは、(ローマで政治決定を下すには)アウグルが吉兆と判断して、その決定を支持する必要があった習慣にちなむ。
エトルリアの影
建国の英雄兄弟の袂を分ったエトルリアの鳥占い
歴史家リウィウス(Livius、英語圏ではLivyとも)が書いた『ローマ建国史』によれば、建国の英雄ロムルス・レムス兄弟は、都をローマに置く際、どちらが拓いた丘を都の中心にするかで争いになり、鳥占いに天意を問うたそうです。
最初、レムスの拓いたアウェンティヌスの丘に6羽の鷲が舞い降りたのですが、その後12羽がロルムスの拓いたパラティヌスの丘に舞い降りました。兄弟は鷲が降りた順番をとるか、数をとるかで血で血を争う対立に至ります。最終的には、ロルムスの亡骸の上に、すなわちパラティヌスの丘の上にローマが築かれることになりました。

躍進の転機となったエトルリア人のローマ改造
この建国神話の後、ローマは王政ローマの時代へ入ります。エトルリア出身のが第五代タルクィニウス・プリスクスが王位に就いた頃から第七代王が追放されるまでの一世紀ほどの間、ローマはエトルリア出身の王が続きました。この時期に、大がかりな水道工事や灌漑工事など急激なインフラ整備が進み、その後の共和政ローマ時代、ローマ帝国時代への発展の礎が築かれます。
エトルリアはギリシャとローマを橋渡ししたといわれます。その意味するところは次のようなことです。
- エトルリアは先史時代の地中海世界が生んだ「最後の一花」だったのではないか(イギリスの作家D.H.ロレンス)。
- 交易の発達によってギリシャ人がエトルリアに移り住むようになると、地元文化とギリシャ文化の混淆が起き、独自のエトルリア文化に発展した(とくに美術)。
- エトルリア文化がローマ人に深い影響を及ぼした。とくに後のルネッサンスの中心地はエトルリアのあったトスカーナ地方(フィレンツェ)であることから、中世以降もその影響は滅びることがなかった。
ロレンスはエルトリアに何を見ていたのか?
『チャタレー夫人の恋人』ばかりが有名で、他はあまり知られていない作家ロレンス(D.H.Lawrence)が生涯憧れ続け、インスピレーションの源泉にしていたのはエトルリアでした。彼のイタリア紀行文集『エトルリアの故地』から引用してみます。
有史以前の世界という暗がりの中から滅び行く様々な宗教の瀕死の姿が浮かび出て見える。それらの宗教は未だ男の神々、あるいは女の神々という人 格神を作り出してはいず、ただ大宇宙に存する根源的な諸力の神秘によって、私たちが今日弱々しい声で自然と呼んでいるものが持つ、あの様々な複合的な生命力によって生きている宗教である。神々も女神たちも、何ら明確な形では未だ出現してはいなかったように見えるのだ。
確かに「東の香り」がするのではないでしょうか?
ロレンスの「いのち」
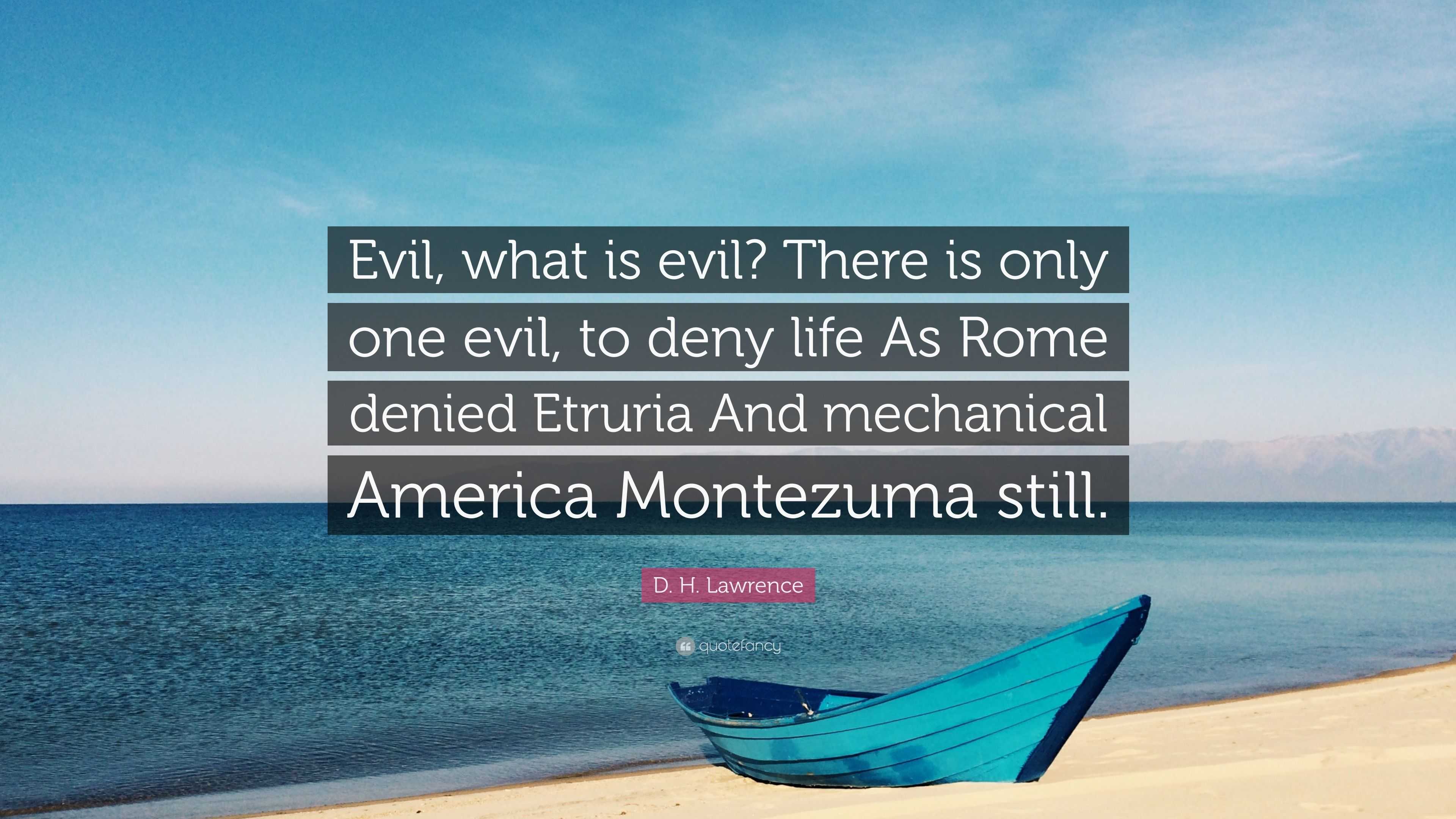
悪魔ー、悪魔とは何か?ローマがエルトリアを否定したように、そして、いまも機械文明のアメリカがモンテスマを否定し続けているように、それはたったひとつしかない。いのちの否定である。(※モンテスマはスペイン人侵略時のアステカ王)。
ここでロレンスのいう「いのち」とは次のような「いのち」のことです。冒頭に書いた古事記の「いのち」と同じ考えに見えます。
有史時代のまさに夜明けの頃の、支那にも、印度にも、エジプト、バビロニアにも、いや太平洋諸島や原始時代のアメリカにも、既に一つの宗教思想が、それぞれの土台に存在していたという明らかな証拠が見られる。即ち宇宙は一つの生きものであり、宇宙を形成している無数の生命は、烈しく入り混じって混沌なる状態にあるが、しかしこの混沌には、依然としてある秩序が保たれているという宗教思想が・・・ そして人間は、この真赤に燃え上がる混沌のただ中に立って、あえて危険をものともせず、力戦苦闘してただ一つのものを、生命を、活力を、さらに多くの活力 を求めるのだ、彼方にきらめく大宇宙の生命力を、さらに多く己れの内部に、いやが上にも掬み入れようとするのである。(『エトルリアの故地』)









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません